Google Colaboratoryで学ぶ 高校情報II×高校数学×探究授業のための
中高生からのPython 問題解決プログラミング・AI理論
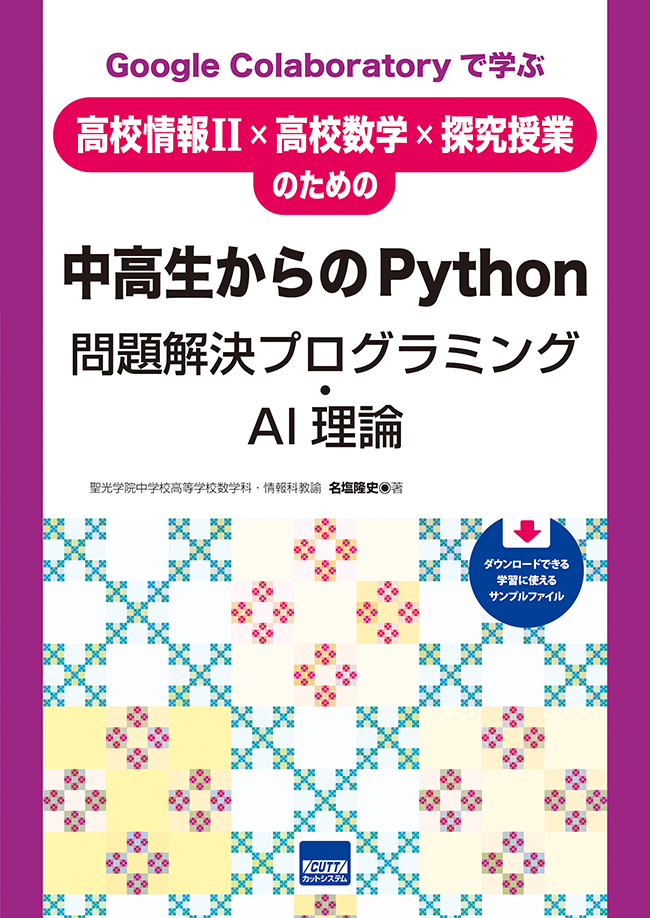
| 著者 | 聖光学院中学校高等学校数学科・情報科教諭 名塩 隆史 |
|---|---|
| 判型 | B5判、304頁 |
| ISBN | 978-4-87783-614-6 |
| 価格 | 本体3200円 |
| 発行日 | 2025年9月10日(初版 第1刷発行) |
本書について
本書は,拙著「中高生からのPythonプログラミング」の続編に当たり,基本事項(if文,for文,while文,関数の定義,1次元配列の使い方)を学び終えた人を対象として,その次の段階,つまりプログラミングを活用して様々な問題を解決する方法,そのために必要とする発展的な文法事項についてまとめたものです。特に,オブジェクト指向プログラミングの基礎となる「クラス」の考え方,AIプログラミングには欠かせない標準ライブラリ「Numpy」「Matplotlib」「Pandas」の基本的な使い方,再帰や探索・動的計画法のアルゴリズムとスタック・キューや木構造・グラフといったデータ構造,さらには機械学習や深層学習といったデータサイエンスの手法とAI理論について,中高生でも理解できる範囲で記述することを目指しました。
目次
- IPythonの中級レベルの文法
- 第0章準備
- 0.1Google Colaboratoryの使い方と生成AIの活用について
- 0.2Pythonの基本の復習(基本構造・配列と関数)
- 第1章2次元配列と再帰・重要文法
- 1.12次元配列
- 1.2再帰
- 1.3技巧的なPython文法
- 第2章クラスとオブジェクト指向プログラミング
- 2.1クラスの概念
- 2.2クラスの継承
- 第3章標準ライブラリの使い方(Numpy,Matplotlib,Pandas)
- 3.1Numpyの使い方
- 3.2Matplotlibの使い方
- 3.3Pandasの使い方
- 3.4Matplotlibでの図形描画(patches)
- 3.5Matplotlibでのアニメーション動画作成
- 3.63DMatplotlibでの3次元図形の描画
- 第0章準備
- II応用実践編
- 第4章関数と配列を活用した問題解決プログラミング
- 4.1カレンダーの作成
- 4.2カードのシャッフル
- 4.3鉄道環状線の運賃表の作成
- 第5章アルゴリズムとデータ構造
- 5.1連結リスト(クラスの応用例1)
- 5.22分探索木(クラスの応用例2)
- 5.3動的計画法(ナップサック問題)
- 5.4グラフとNetworkxの使い方
- 5.5キューとスタック・探索のアルゴリズム
- 第6章フラクタル図形の描画と動画シミュレーション
- 6.1数学からの準備(ベクトルと三角関数)
- 6.2フラクタル図形の描画
- 6.3シミュレーション動画の作成
- 第7章統計分析と機械学習
- 7.1Pandasによる統計分析の基本(購買データ)
- 7.2データベースの整理(購買データ)
- 7.3正規分布と2項分布
- 7.4scikit-learnを用いた機械学習入門
- 7.5機械学習を利用した社会統計データ分析
- 7.6GeoPandasを用いた統計地図の作成
- 第8章画像処理と手書き数字の認識
- 8.1OpenCVとカラー画像の生成・3次元配列
- 8.2カラー画像の処理
- 8.3手書き数字の認識
- 8.4画像のアフィン変換
- 第9章深層学習(Deep Learning)入門
- 9.1深層学習とニューラルネットワーク
- 9.2数学からの準備(関数の微分と合成・偏微分)
- 9.3誤差逆伝播法によるパラメータの更新
- 9.4Kerasを用いた誤差逆伝播法による深層学習の実装
- 9.5畳み込みニューラルネットワーク(CNN)の仕組みと実装
- 9.6自然言語処理の概要と生成AIの利用上の注意点
- 第10章強化学習入門
- 10.1強化学習とバンディット問題
- 10.2マルコフ決定過程
- 10.3数学からの準備(Σ記号と期待値)
- 10.4ベルマン方程式とQ関数
- 10.5ベルマン方程式の数値計算による解法
- 10.6ベルマン最適方程式とQ学習
- 第4章関数と配列を活用した問題解決プログラミング